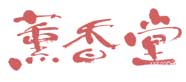|
香木、線香、ねり香、塗香、抹香、焼香、匂い香に分けられる。 香木は、沈香類、白檀などの原材を、小さく割り、香炉を用いてたく。香道では、 沈香のなかでも上質のものしか使わない。 線香は、各種の香料とタブノキの皮を練りあわせ、細い棒状にしたもので、室内線香、 仏事線香、香水線香など、目的によってさらに分類される。 ねり香>は、各種の香木や香料を粉末状に刻み、蜂蜜や梅肉、炭の粉を練り固めた 丸薬状の香である。お茶席で炉のなかの灰のうえに置き、温めて香りを出すか、 香炉を用いて香りを楽しむ。ねり香の一種には、原料を練りあわせ、梅型や楓型にく りぬいた干菓子状の印香もある。 各種の香木や香料を粉末状にしてあわせたものに塗香と抹香がある。 塗香は、体に塗って、体臭を消し、身をきよめるために使われる香である。現在 でも仏式儀式の前には、「きよめ香」としてこの粉末を体に塗ったり、大きく息をすいこんで 体内をきよめることが行われている。 抹香は、そのままで香りを放つようにした、ひじょうに細かい粉末である。また、 長時間くゆらせておく香盤などにも用いられる。 焼香は、香木や香料を細かく刻んで混ぜあわせたもので、霊前でたく香である。 用いる香木や香料により五種香、七種香、十種香などがある。本来は沈香、白檀、 丁子、鬱金香(ショウガ科の多年草の根茎からつくられる香料)、竜脳の五種の組み あわせを基本とするが、高価になってしまうので、他の香料で組みあわせることも 多く、それらは香りも落ちる。 匂い香は、白檀、竜脳、薬草などの香料を細かく刻んで混合し、火を使わない状 態で香りが発散するように配合されたものである。袋に入れ、タンスに入れたり柱 にかけたりする。また、車のなかにも香りのアクセサリーとして用いられている。
インドで、時をはかる道具、すなわち現在の時計として使われていた。 仏教が起こり、釈尊の入寂後に霊前に香が用いられるようになり、線香の使いやすさ、 便利さからしだいに仏教の世界で使われるようになったのである。 現在、日本で一般に線香と呼んでいるものをつくる技術が伝来したのは四百年ほど前の 天正年間で、比較的歴史が新しい。 朝鮮からの帰化人が長崎でつくりはじめたという説と、中国福建省福州から 五島一貫(帰化人ともいわれる)が堺に技術を伝え、当時の都であった京都に定着した という説がある。 現在つくられている線香は、目的によって長さや形が幾種類もあり、また断面も 丸状と角状の二種がある。香りも、各製造会社によって調合が異なるのでさまざまである。 家庭用高級線香は、仏前のほか、座敷、応接室、書斎などの室内で、香りを楽しむために たかれる線香である。伽羅をはじめ、沈香、白檀、桂皮、丁子、麝香、竜誕香 などの香料を用いる。最高級な香料を使った数万円・数10万円という高価な種類もある。 香水線香は、バラ、ユリ、梅などの花の香りや、レモンなどの柑橘系の香料が配剤されている 線香で、室内でたいて楽しむことができる。 寺院用長尺線香は、寺院の儀式に用いる線香で、式の間 香りがたえないように、 使用時間にあわせた長さにつくられている。長いもので73センチあり、約八時間もつ。 実用線香は、一般家庭の仏壇で使われるもので、配剤する香料の種類、量は各線香に よってまったく異なる。長さは、14〜18センチがふつうである。 輸出用線香は、明治三十年ごろから、欧米への輸出用としてつくられたものである。 灰が散らばらないように、円錘形をしている。だが最近では国内向けにも出まわっており、 室内香として人気がある。 杉線香(墓地線香)は、杉の枯葉や実を細かく粉末状にし、中国・ベトナム産の支那粉と 呼ぶ粘着剤を用いた線香で、もっとも安価である。 このほか、線香にはうず巻き形の線香もある。 直径10センチにもみたないうず巻き線香は、 座敷や客間用のもので、ふつうの線香より長時間、芳香を漂わせたいときに便利である。 うず巻き線香1個で2〜3時間は燃えつづける。 もともと線香は、よい香りを長時間保たせるために発明されたのだが、この点をさらに 工夫したのがうず巻き状の線香といえる。 一方、仏前用のうず巻き線香もある。これは、おもに関西地方で用いられるもので、 ふつう座敷用のうず巻き線香や蚊とり線香も平面状のまま使用するが、仏前用の うず巻き線香は、まんなかをもつと、つり鐘状になるので、長時間燃やすことができ、 49日間火をたやさないという仏事の習慣にかなっている。 つり鐘状になるうず巻き線香のなかには、2メートル以上の長さの大型のものもあり、 それは数日もつという。
実用線香から、部屋によい香りを漂わせる座敷用の高級線香、花の香りなどを とり入れた香水香と、さまざまなものが売られている。種類も豊富なら、値段もピ ンからキリまである。 そこで気に入った香りの、かつよい線香を見つけるにはどうしたらよいか。 香りの好みには個人差があるので、値段が高ければいいというものでもない。 だが、選ぶにはちょっとしたコツがある。 よい線香ほど、点火する前の線香自体の においではわからない。香りの判定は点火した線香を鼻の前2、3十センチほどのところを 2、3回通過させ、試し聞きす 線香は、火がついて燃えている部分から芳香を放っているように見えるが、じつはそうではない。 燃える熟で、その二、三ミリ下の部分が温められ、よい香りを放つしくみになっている。 したがって、鼻の前でとめて芳香を煙といっしょにめいっぱい吸いこんでしまっては 微妙な香りがわからなくなるのである。 また、線香をたいた部屋のとなりの部屋にいて、流れてくる香りを賞味して鑑定するのも、 ひとつの方法である。 なお、たく際には、異種の香りの線香を同じ香立でいっしょにたくことは、さけたほうがよい。 そのほか、香をたくときに、線香を折って火種にすることなども、よい香りをさせるためには さけるべきことである。 日常の手入れとしては、しめり気の少ない、直射日光のあたらない暗所に保管するのがよい。
うどんをつくるとき、原材料の小麦粉だけではめんが折れやすいので、 たまごなどのつなぎを加える。線香の場合は、つなぎに粘着力のあるタブノキ というクスノキ科の常緑高木の樹皮の粉末を使う。 ノリ粉という、タブノキの葉を粉末にしたものもあるが、こちらは臭気があるため、 におい線香には使用しない。 もともと線香は″繊香″と書かれていたが、線香をよく見てみると、細かな繊維がからみあって できていることに気づく。これは、タブノキの甘皮の繊維であり、繊香の由来もそこにある。 つくり方は、まず、材料を混ぜ、熱湯を加えて何度も練りあわせる。そして染料を入れて 色をつけるが、これは、乾燥過程で、他の種類の線香と混ざらないように区別するためである。 これを押し出し機にかけると、小さな穴から何本ものそうめん状のものが出てくる。 この穴が均一なために、同じ太さの線香が生まれるのである。 そうめん状の線香を盆に受けとり、竹べらで切りそろえる作業を。”盆切り”という。 つぎに乾燥板に移し、それぞれの製品にあった寸法に切りそろえる。これをで、ぎっしりと 詰めて並べなくてはいけないからである。 並べられた生の線香は、3、4日かけて自然乾燥させる。″生付け″というが、400本近い 生の(やわらかい)線香を、竹べらでそろえていく作業は、相当熟練していないとできない。 線香と線香の間にすき間ができると、乾燥機にかけるときに曲がって不良品となるのだが、 乾燥場のスペースや雨期にカビが発生するなどの問題があるため、製造所によっては 自然乾燥にたよらず、機械による乾燥方式をとっている。 この方式により、乾燥時間の短縮をはかっているのである。 線香づくりのむずかしさは 香料とタブノキの配合比率や、熱湯の量の微妙なかげんによって、曲がったりそったり、 また点火してもすぐ消えてしまったり、折れやすかったりすることである。 したがって、線香は、いかに機械化が進んでも、長い間つくりつづけてようやくかげんがわかる 熟練の産物といえる。原料の100八ーセントが天然産であるだけに、完全機械化が できにくく、微妙なむずかしさがある。
日本に伝えたといわれている。 中国には6世紀のころ、すでに陶弘景という合香家、つまり香料を配合する調香師がいて このねり香をつくり、市販していたようである。 つくり方は、まず各種の香料を粉末にするが、それには、理由があって、中国の 顔特約は『香史』のなかで、つぎのように述べている。 「粉末のほうがもとの大きなものより、香気の発散率が高い。細かすぎても香の煙は 長くつづかず、粗いと香気が和合して一体にならない。したがって臼のなかでよくひき、 大きさを平均にさせなければならない」 細かく粉末にしたこれらの香料に、蜜を加えるが、中国では蜜のほかに、石蜜、蔗糖、 葵の葉と花に薄い糊を加えたものなどを人れていた。 日本では梅肉を加えることもあり、鑑真和上が伝えたという資料では、蜜になっている。 なぜ、これらを加えるのかといえば、やはり粉末にした香料だけでは、名前のように 練ることはむずかしい。そこで香料のつなぎとして用いるわけである。 現在は、蜜として蜂蜜を用い、厳選したくせのない、腰のあるものが使われている。 また、ねり香は、つねにしめり気を保たせる必要から、蒸発する性質をもつ水を 一切使わない。しめっているために、ねり香独特の深みのある芳香が出るのである。 6、7世紀の唐の『斉民要術』『新条本草』などには、甘蔗(サトウキビ)、砂糖の生産量が 増加していると書かれているが、それもこのねり香と関係がありそうだ。 さて、こうして蜜を用いて練られた香料を配合した直後は、香りが浅く、それぞれの香料が 融合しない。そこでつぎなる工夫が必要となる。 12世紀初めの洪芻の『香譜』によれば、「よくひき砕いて細かい粉末とし、蜜を加えて よく練り固め、新しい瓷器のなかに貯え、密封して地中に埋める」 とある。 つまり、ウイスキーと同じで、寝かせれば寝かせるほど、芳醇で、深みとまるみのある 上品な香りとなるわけである。最低三年は寝かせるとよいといわれる。 ねり香は、現在でもすべて手づくりである。香木を粉末にする作業も、機械を使うと 熱が発生して香りのうちの三分の一が逃げてしまうため、手で刻む。また、練りあげや 丸形などに形を整えるのもすべて手作業である。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|