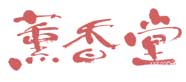|
「お香」もひとくちに言っても、その種類や作り方やかたち、用いる場所によって実にさまざまです。いかに高級なお香と言えども、使い方を知らなかったり誤った使い方をしては、せっかっくの香りも台無しになってしまいます。 ほんの少し気をくばっていただくと、香りは驚くほど引き立ってくるものです。良い香りを引き出す基本のコツは、お香の個性に合わせて使い分けることと言えるでしょう。 ここではさまざまなお香の種類と、そのじょうずな使い方の一例をご紹介します。うまく使いこなしてくらしをお香で彩ってみませんか。
主にご家庭で仏事に使われる10〜30cm程度のお線香は、宗派などによって炊き方が異なりますが、一般的には「仏・法・僧」の原理にしたがって、香炉の中で1本ずつ三方に立てることが多いようです。原料に伽羅や沈香を多く用いた高級線香は、仏事だけでなく、お部屋で楽しむ香りとしてお客様のおもてなしにもお使いいただけます。 「長いお線香」 座禅香とも言われています。禅堂で用いる70cm以上の長さの物もあり、大型の香炉に立てて使います。法要の導師用としても使用されることもあります。 「短いお線香」 花やフルーツ、スパイスの香りなど、バラエティ豊かな香りをお部屋で楽しむお香として10cm未満のものもあります。お好みの香炉や香皿に立ててお使いください。 「コーン型のお香」 短時間に強い香りを出すことができるうえ、灰を散らさないため、人気の高い、使いやすいお香です。円錐の先端に点火し、そのまま香皿や灰の上に置いてお使いいただけます。 「渦巻き型のお香」 長時間炊き続けることができるので、広い空間や、空気の流れの多い玄関などでのご使用に適しています。専用の香皿や香立てを用いるほか、よく乾燥させて灰を香炉に敷きつめ、その上に直接のせて焚くもよいでしょう。この方法なら、折れて短くなったお香も、最後までむだなく焚くことができます。 「焼香」 香木などの天然香料を細かく刻んで調合したお香。仏前で、直接炭団や炭火の上に薫じます。 「抹香」 非常に細かい粉末のお香で、古くは仏塔や仏像などに散布していました。仏前で焼香のときなどに用いたり、長時間くゆらせておく時香盤や密教用具の火舎などにも使われます。 「空薫(そらたき)」 着物やお部屋にお香を焚きしめて、自由に香りを楽しむことを、古来「空薫]と表現されてきました。むずかしい作法や道具にとらわれず、おおらかにいろいろな香りを楽しんで昧わってみてください。香りの世界を、より広く知ることができるでしょう。
香木など天然香料を粉末にして、古典的な製法のまま丸薬状に練りあげたもので、「源氏物語」などに登場する薫物を今に伝えるお香で礼深く重厚な香りで、茶の湯の席で冬の香りとして好まれるなど寒い季節に使われることが多いようです。 Oお茶席で用いる場合 炉中の熱灰のそばに2粒ほど置かれます。 ○ご家庭で用いる場合 香炉や火鉢の熱灰の上にのせたり、小さなアルミカップに数粒を人れて、ストーブの上で熱して香らせたりします。また電気式やガスライター式の香炉などで、手軽に楽しむことができます 「印香」 粉末にした香料を練り合わせ、梅花やもみじのかたちに型抜きして乾かしたもの。練香と同じく、熱灰の上こ のせて薫じます,浅く軽い香りで、夏の風炉中などで用いられます 「香木」 沈香と白檀のl種類が代表的です。沈香のなかでも、伽羅は古くから品位の高い最上の香りとして珍重されてきました。茶の湯の席では、主こ風炉の時期に用います香舗などで、薄い角割にしたものをお求めになると扱いやすいでしょう。
もっとも粒子の細かいお香で、片栗粉のようになめらかです。俗に清め香ともいわれるように主に密教寺院などで、本尊こ供えたり、読経や写経の祭に手やからだに少量を塗って心身を清めたりするために使用します。 「匂い香・掛香」 王朝文学などに散見できるように、古来、衣裳の防虫に使われてきました。天然香料を刻んで調合し、袋に詰めて使用します。現代では、くるまの中やのれんに吊るほか、身につけたり箪笥に人れたりして衣服への移り香を楽しみます。少し大きめのものは玄関先などに置いて、美しい形と香りを楽しむのもよいでしょう。匂い袋は、たいていビニール製などの外袋に人れられていますが、はじめは香りが強いものですから、外袋のまま衣裳箪笥のすみに置いてご使用ください。また、中のお香だけをお求めいただき、自作の匂い袋に詰めるのも楽しいものです 「防虫香」 古書や掛け軸、お人形などの虫よけ用に調合されたお香です。香袋が品物に直接触れないように、和紙などで包んで、箪笥や箱のすみへ置いて下さい。また白檀の香りは防虫効果が高く、木を薄くスライスした物を敷いて使うこともあります。衣装用にお使いいただくこともできます。 「お香を食べた」 平安時代のお香はすべて「唐物」。その唐や隋では陳皮や麝香を内服していたそうです内服しはじめて5日経つと体から香りが立ち、1ヵ月もすると、抱いた子供にまでその香りが移ったとか。念のため、現代の私たちが普段使うお香は食べられませんので、ご注意を。、
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|